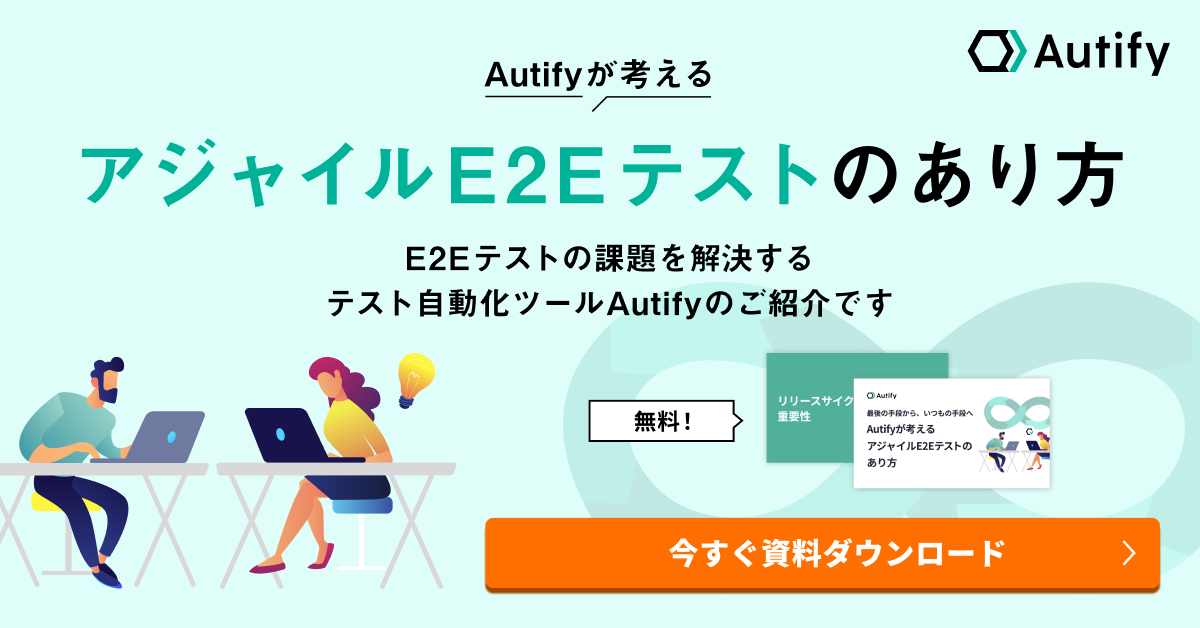E2Eテストとは?基本から効率化の手法・他のテストとの違いを解説

E2Eテストはユーザー視点でソフトウェアの機能を確認するブラックボックステスト手法です。ソフトウェアの品質に直結するUX(ユーザー体験)のテストであることから、ユーザーの満足度に大きく関わるため、重要な位置付けのテストです。
本記事ではE2Eテストの実施ハードルの高さやそれを乗り越えるメリット、具体的な自動化の進め方を解説します。
E2Eテストの基本
E2E(End to End)テストとは、ソフトウェアテストの一種であり、システム全体が要件どおりに機能するかどうかを検証するために行われるテストです。
E2Eテストの基本事項や他のテストとの違いについて確認しましょう。
E2Eテストとは
E2Eテストとは、ソフトウェアの総合試験の1つであり、ユーザー視点で動作を確認するテストです。
E2Eテストはユーザーの操作を基点とするため、ブラックボックステストに分類されます。プログラム内部の構造を知らなくても、ソフトウェアが正しく動作するか、意図した通りに機能するかを検証できます。
例えばECサイトのE2Eテストでは、「商品検索 → カート追加 → 決済 → 注文確認」といった一連の操作フローを、実際のユーザーと同じ手順で確認します。
また、E2EテストはWebブラウザやフロントエンドアプリケーションを通じて操作を行い、ソフトウェア全体の挙動を検証する点が特徴です。
システムテストとの違い
E2Eテストとシステムテストは、テストの範囲に違いがあります。
システムテストは総合テストの1つで、システム全体が機能要件を満たしているかを確認するテストです。ソフトウェア全体を対象にするため、E2Eテストよりも範囲が広いのが特徴です。一方、E2Eテストはユーザー視点での操作や挙動を確認することに重点を置いています。
テストの進め方にも違いがあります。システムテストでは、機能単位や画面単位でテストケースを作成し、統合されたソフトウェア全体を検証します。例として、画面ごとの入力チェックや機能単位の動作確認などが挙げられます。これに対してE2Eテストでは、ユーザーが実際に操作する一連の流れを検証します。
そのため、E2Eテストはシステムテストの一部として位置づけられるテストといえます。
結合テストとの違い
E2Eテストと結合テストは、実施するタイミングが異なります。
結合テストは、複数のモジュールや機能を組み合わせた際に正しく連携するかを確認する工程です。内部の処理やデータの受け渡しを精査するため、ホワイトボックステストの要素を含むことがあります。
例えばECサイトの場合、商品検索機能と商品詳細表示機能の連携を確認するテストが挙げられます。ユーザーが商品を検索して選択した際に、詳細画面が正しく表示されるかどうかを検証する項目です。これらの連携が担保されていなければ、E2Eテストで「商品検索 → 商品選択 → 購入」といった一連の流れを確認することはできません。
そのため、結合テストを終えて総合テストへ進んだ段階で、E2Eテストが実施されます。
E2Eテストの重要性
E2Eテストが重要な理由として以下が挙げられます。
- UX向上につながりやすい
- ユーザー視点でないと気付けないバグを検出できる
- リグレッションテストの役割も兼ねる
UX向上につながりやすい
E2EテストはUX(ユーザー体験)の向上につながりやすいことが、重要視される理由の1つです。
E2Eテストは、実際のユーザー操作をシミュレーションしながら、アプリケーション全体が意図通りに動くかを確認します。よってテスト担当者は「UX向上のためにはここが使いにくい」「これができるとユーザーはより使いやすいサービスになる」などユーザー目線での発見、フィードバックが可能です。このフィードバックがソフトウェアの改善アイデアとなり、結果としてUXの向上につながります。
UX向上は売上増加や販売促進など業績にも直結するため、E2Eテストは単なるバグ検出だけでなく、事業成長のための重要なプロセスとして位置づけられています。
ユーザー視点でないと気付けないバグを検出できる
E2Eテストはユーザー視点でないと気付けないバグを検出できる可能性があることも重要視される要因です。
単体テスト、結合テストなどのホワイトボックステストを実施しても検出できないバグが潜むことは往々にしてあります。逆に考えると、これらで検出できないバグでもE2Eテストだと発見できることがあります。例えば、実際のユーザー操作に沿った一連の流れでしか発生しないバグや、UI上の予期しない挙動などです。
ユーザー視点でないと気付けないバグを検出、修正できれば、ソフトウェアの品質や信頼性を維持、向上できることから、E2Eテストは重要視されています。
リグレッションテストの役割も兼ねる
E2Eテストは、リグレッションテストとしての役割も果たすため重要視されています。
リグレッションテストとは、既存機能が新たな変更によって影響を受けていないか、いわゆる「デグレードが発生していないか」を確認するテストです。
E2Eテストでは、ユーザー目線で操作を再現することで、既存機能に問題がないことを確認できます。本番環境と同様の操作を自動で繰り返すことで、目に見えない副作用や予期せぬバグを早期に検出し、品質の劣化を防ぐことが可能です。
さらに、E2Eテストを用いたリグレッションテストを行うことで、既存ユーザーへの影響を未然に防ぎ、顧客離れのリスクも低減できます。
関連記事:リグレッションテスト(回帰テスト)とは?デグレを防ぐ最新のやり方・自動化の方法を紹介
E2Eテストの課題
E2Eテストを実施する上での課題として以下が挙げられます。
- テスト設計が難しい
- テスト工数が大きい
- テスト自動化が難しい
テスト設計が難しい
E2Eテストの実施ハードルが高い要因として、テスト設計が難しいことが挙げられます。
E2Eテストでは、ユーザーの操作を正確に再現する必要があることから、複雑な業務フローや分岐を含むテスト設計が必要になるケースがあります。ユーザーの操作シナリオを網羅しようとすると膨大なパターンを洗い出す必要があるため、曖昧な仕様やUI変更にも設計が影響を受けやすいです。
E2Eテストは設計段階から高い理解力と経験が求められるため、実施ハードルが高くなっています。
テスト工数が大きい
テスト工数が大きいこともE2Eテストの実施ハードルが高い要因です。
E2Eテストは設計ができても、実施自体の工数も大きいケースが多くあります。システム全体を通して動作確認を行い、テスト実行時間が長くなるためです。またテスト結果が一定にならないケースや、自動化が難しいケースもあり、テスト工数削減の取り組みがしにくい面があります。
加えてE2Eテストの準備や検証、障害時の調査・復旧にも時間がかかり、他のテストと比べてコストが高くなりやすいため、E2Eテストの実施をためらってしまうケースがあります。
テスト自動化が難しい
E2Eテストは、自動化が難しいケースが多いテストです。
UI操作を伴うため、画面構造や要素の変更の影響を受けやすく、特に動的に変化する画面や非同期処理の多いソフトウェアでは、テストの安定性を保つのが難しくなります。その結果、自動化ツールのメンテナンスコストが高くなることもあります。
また、自動化にはプログラミングやツール操作のスキルが必要です。ノーコードやローコードのツールを使用しても、習熟には時間がかかりますし、ツール導入や実装にも一定のコストが発生します。
このように、技術面とコスト面の両方のハードルが、E2Eテスト自動化の実施を難しくしています。
それでもE2Eテストを自動化すべき理由
E2Eテストは実施ハードルが高いことを先述してきました。それでもE2Eテストを自動化すべき理由として以下があります。
- テスト工数の削減ができる
- 繰り返し実施できる
- テスト結果が安定する
テスト工数の削減ができる
E2Eテストを自動化すればテスト工数の削減が可能です。
先述したように、自動化のハードルは高いですが、自動化することで手動よりもテスト工数削減が期待できます。例えば、従業員退勤後の夜間に自動化ツールがテストを行うことで、従業員は出社後に結果確認をするのみ、となればテスト実施の工数を大幅に削減可能です。
自動化によりテスト工数を削減することで、プログラム修正、開発、さらなるテストなど別の活動に時間を使えます。
繰り返し実施できる
E2Eテストを自動化できれば、同じテストを繰り返し実施できるようになります。
CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインやアジャイル開発など開発サイクルの迅速化に伴い、テストも頻繁に実施する必要があります。これらのツールや開発手法は細かい機能単位で開発が行われるため、1週間に複数のテスト実施を継続的に求められるケースもあるでしょう。しかし、開発や修正のたびに手動でテストをしていてはスピーディなサイクルに間に合いません。
自動化できていれば、開発が完了したプログラムに対して、サイクルに合わせたスピード感でE2Eテストが可能です。これにより品質を落とさずに短期間でのリリースや頻繁な機能追加が実現し、相乗効果を期待できる開発サイクルになります。
テスト結果が安定する
E2Eテストを自動化できていればテスト結果が安定します。
仮にGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)や仕様が変更されていなくても、E2Eテストを手動で行うとテスター(テスト実施者)ごとに結果が異なってしまうケースがあります。自動化によって誰が実行しても同じ結果が得られるため、テストの信頼性を高めることが可能です。テスト結果の安定はソフトウェアの品質保証において重要な意味を持ちます。
ただし、GUIや仕様変更があれば自動化ツールを使ってもテスト結果が安定しない場合もあることは頭に入れておく必要があります。テスト対象の安定と、テスターによるテスト品質の両方が安定することが望ましいですが、テスト自動化は後者の安定化につなげることが可能です。
E2Eテストを自動化するアプローチ
E2Eテストを自動化するアプローチは以下の通りです。
- 自動化ツールの選定
- テストシナリオの作成
- テスト自動化の実装
- 自動化ツールのテストを行う
- CI/CDパイプラインに組み込む
1. 自動化ツールの選定
E2Eテストを自動化するにあたり、まずはテスト自動化ツールの選定を行います。
どのテスト対象に自動化をするのか選択し、現実的に自動化が可能なツールを選択しましょう。このときに、ブラウザやソフトウェアのバージョンなど互換性を忘れずに確認する必要があります。またその他の比較要素として、予算や、テスターが問題なく使えるか、実装時にプログラミングが必要か(ローコードやノーコードか)の確認も必要です。
また昨今のテスト自動化ツールにはAIが導入されており、テストケースの作成や自動化を行ってくれるツールも存在します。Autifyは生成AIが組み込まれているツールであり、テストケースの作成や、テスト実行をAIが担ってくれます。これにより、開発サイクル全体の短期化が可能です。
2. テストシナリオの作成
自動化ツール選定後、テストシナリオを作成します。
テストスコープを決めておき、自動化するテストの内容を考える工程です。基本的には自動化のことを考えずにE2Eテストとしてどんなテストを行うのか、設計すればE2Eテストとしては問題ありません。
例として、ユーザーが入力した内容に沿ったリソースを作成できるのか、ボタンをクリックした際に正しく画面遷移ができるかなどソフトウェアのユースケースに即したテスト内容を考えます。
テストシナリオの作成ができることで、具体的に自動化につなげることが可能です。
3. テスト自動化の実装
作成したテストケースに基づき、実際に自動化を行うための実装を進めます。
選定したツールに合わせて、プログラミングやローコード・ノーコードのフローチャート作成などの工程を実施しましょう。プログラミングの場合は、各機能のコードを疎結合に設計することで、保守性を高めることができます。ローコードやノーコードを使用する場合も、共通化できる部分をあらかじめ検討しておくと、実装コストを抑えやすくなります。
こうして実装を行うことで、テスト自動化の準備が整います。
4. 自動化ツールのテストを行う
実装が完了したテスト自動化ツールのテストを行って、テスト品質を担保できることを確認します。
実装が完了しても、すぐに本番運用を開始できるわけではありません。実際にテスト結果が期待通りになるかを確認する必要があります。意図していたテスト結果と同じになる、あるいは明らかに問題がない結果になることを確認してください。ただし、意図した結果と異なる場合はツールに問題があるのか、設計したシナリオに問題があるのかよく見極める必要があります。
自動化ツールのテストが完了して、ようやく本番運用に乗せることができます。
5. CI/CDパイプラインに組み込む
テスト自動化ツールをCI/CDパイプラインに組み込むことで、さらに効率的な自動化が可能になります。
CI/CDパイプラインに組み込むことで、ソフトウェアの改修が行われた際にも、E2Eテストを含む自動テストをすぐに実行できます。E2Eテストは準備や結果確認に手間がかかりますが、CI/CDパイプラインに統合されていれば、これらのコストを最小限に抑えられます。
そのため、極力CI/CDパイプラインに組み込めるよう、ツール選定や連携方法をあらかじめ検討しておくことが重要です。
まとめ
E2Eテストは、ユーザー視点でシステム全体の品質を確認できる重要なテストです。しかし、テスト設計や工数など多くの課題があります。それでも自動化を進める価値は大きく、繰り返しの実行や結果の安定化、工数削減などのメリットは開発スピードと品質向上の両立に直結します。
E2Eテストの自動化は一度構築して終わりではありません。成功のためには、適切な自動化ツールの選定を行い実装と改善によるプロセスを回していくことが重要です。
AutifyはE2Eテストの課題であるテスト設計や実装の難しさを生成AIのサポートによって低減できます。自社のソフトウェアテストに課題がある場合、ぜひお問い合わせください。