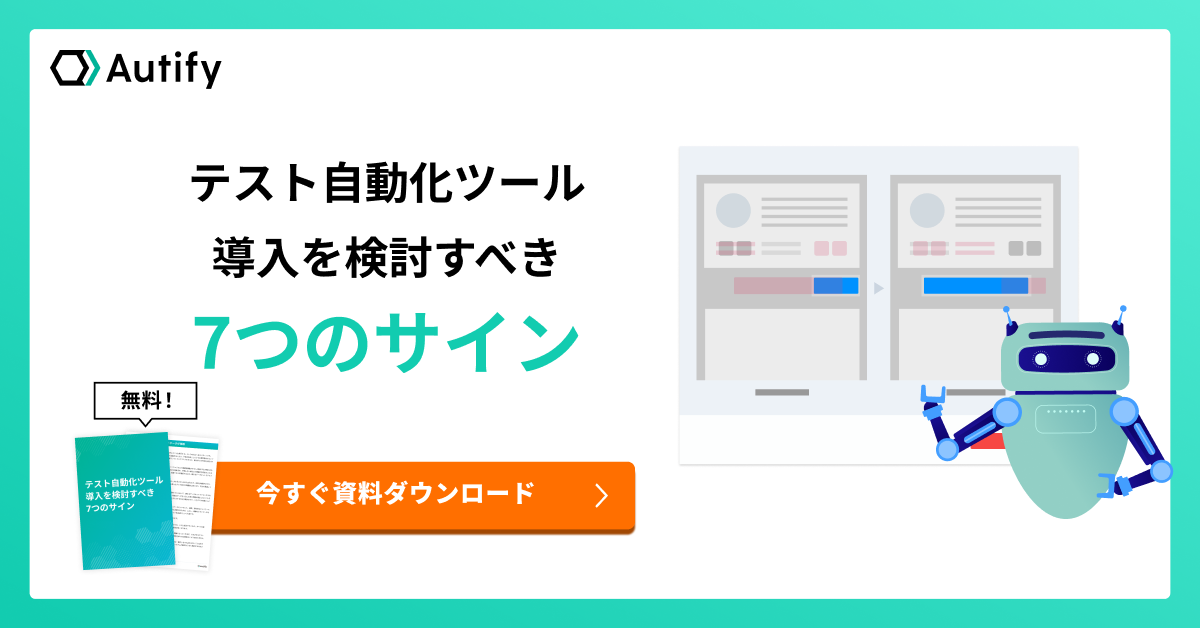定期バージョンアップのテスト課題をAIで解決|効率的な自動化手法を解説

クラウド型のERPやCRMなどのパッケージ製品を利用する企業にとって、定期的なバージョンアップへの対応は避けられない課題です。
Salesforce やSAP といった主要なクラウドサービスは、年に数回のペースで機能追加やセキュリティ強化のためのバージョンアップを実施しており、企業はその都度、自社の業務システムに影響がないかを確認する必要があります。
本記事では、定期バージョンアップに伴うテストの必要性と課題、そして効率的な対策方法について詳しく解説します。
パッケージ製品の定期バージョンアップとテストの必要性
クラウド型で提供されるERPやCRMなどのパッケージ製品には定期バージョンアップが存在します。
ここでは、パッケージのバージョンアップに関する課題について解説します。
クラウド製品における定期バージョンアップとは
Salesforce やSAP などのクラウド型業務アプリケーションパッケージ製品は、ベンダーが定めたスケジュールに基づき、年に数回、定期・不定期のバージョンアップが実施されます。
バージョンアップの内容は、新機能の追加や既存機能の改善、バグ修正、セキュリティ修正などです。更新内容はUI(ユーザーインターフェース)や機能仕様の変更、非推奨機能の廃止など多岐にわたるため、場合によってはユーザー企業の業務プロセスやカスタマイズ部分に影響を及ぼす可能性があるでしょう。
これらのバージョンアップにより、常に最新の機能とセキュリティが提供される一方で、企業側では定期的な対応が必要となります。特に、業務の中核を担うシステムにおいては、バージョンアップによって業務に影響が出ないことを確認する必要があります。
定期バージョンアップの頻度とその影響
提供されている製品ごとに更新頻度は異なりますが、多くの製品は定期的にバージョンアップが実施されます。
例として、ERPパッケージとして大きなシェアを誇るSAPは、概ね2年ごとにメジャーアップデートを実施しています。また、CRMを中心として、全世界で利用されているSalesforceのメジャーアップデートは、春・夏・冬の年3回の実施です。
オンプレミス製品であれば、次期バージョンの導入時期やバージョンアップ可否を選択できます。一方で、クラウドベンダーは計画に沿って一方的にアップグレードを実施するため、ユーザーは限られた期間で対応せざるを得ず、本番環境に想定外の影響が及ぶ可能性があります。
この強制的なバージョンアップサイクルに対し、各企業では計画的な対応が必要です。この対応業務は、IT部門や業務部門の年間スケジュールに大きな影響を与えることになります。
定期バージョンアップに対してテストが必要な理由
定期バージョンアップに対するテストの重要性は、主に2つの視点から考える必要があります。
1つ目が、「現在利用している機能が引き続き正常に動作し、日常業務に影響が発生しないこと」です。デグレード(機能の後退)を防ぐための確認であり、業務継続性を担保する上で非常に重要な観点となります。
もう1つが、「カスタマイズしている機能への影響確認」です。パッケージ製品の中には、拡張機能をインストールしたり、追加でプログラムやモジュールを開発してカスタマイズしたりできる製品が存在します。
独自の業務プロセスに合わせて開発した機能は、パッケージ製品のコアシステムの変更により予期せぬ動作をする可能性があります。特に、APIの仕様変更や内部処理の変更は、カスタマイズ部分に直接的な影響を与えることがあります。
オンプレミス製品であれば、リスクを避けるためにバージョンアップを見送るという選択も可能ですが、セキュリティに関する修正が実施されている場合は、何かしらの対応が必須です。
定期バージョンアップのテストで重要な3つの視点
自社で導入しているパッケージが定期バージョンアップに対するテストを実施する場合、観点を絞って効率的にテストを進める必要があります。ここでは3つの視点を紹介しますので、テストの計画を作成する際の参考にしてください。
1. 品質担保のためのテスト戦略
パッケージのバージョンアップに伴い不具合が発生しないことはもちろんのこと、業務に影響を与えないことを第一に考えてテストを実施する必要があります。
特に、既存機能のバージョンアップには注意が必要です。その既存機能に機能追加があった場合や仕様変更があった場合、業務利用に想定外の影響を与えることも考えられます。
仕様変更が目に見えないことがあるため、リグレッションテストの網羅性確保が必要です。仕様変更が文書化されていない場合や、変更内容が明確でない場合もあるため、重要な業務プロセスについては包括的なテストシナリオを準備し、確実に実行する必要があります。
2. 迅速な対応を可能にするテスト体制
年に数回のバージョンアップが行われるようなパッケージ製品の場合、迅速に検証・判断する体制が必要です。
直近のバージョンアップに対応しているうちに次のバージョンが公開され、対応が間に合わなくなることも考えられます。そうなると、テスト担当者は常に対応に追われ、充分なテストが実施できないままバージョンアップを迎える可能性があります。
次のバージョンアップが実施される前に検証を終了させるためには、効率的なテスト実施が必要です。限られた時間内で確実にテストを完了させるためには、テスト計画の標準化と実行プロセスの効率化が重要な要素となります。
3. 持続可能なテスト工程
定期バージョンアップへの対応は一時的な取り組みではなく、継続的に実施される活動です。そのため、特定の個人に依存した体制では、担当者の異動や退職によってナレッジが失われ、対応品質が低下するリスクがあります。
詳細なテスト手順書を作成することは重要な対策の1つですが、手順書のメンテナンスコストや、新しいメンバーへの教育期間を考慮すると、ドキュメントベースの対応には限界があるでしょう。
持続可能な体制を構築するためには、プロセスの標準化と自動化を組み合わせた仕組み化が必要です。テストの実施方法、結果の記録、問題の報告といった一連の流れを組織的に管理し、誰が担当しても同じ品質でテストを実施できる環境を整備することが、長期的な安定運用の鍵となります。
定期バージョンアップ対策における3つの課題
クラウド製品では「バージョンアップをスキップする」という選択肢が基本的に存在しないため、企業は各バージョンアップに対して確実にテストを実施する必要があります。しかし、この継続的な対応にはさまざまな課題が伴います。
ここでは、多くの企業が直面する3つの課題について解説します。
工数の肥大化
バージョンアップのたびに実施が必要なテストケースは、企業規模や利用範囲によって数百から数千に及ぶことがあります。
さらに深刻なのは、システムの利用が進むにつれて、新機能の追加やカスタマイズの範囲が広がることで、テストケース数が継続的に増加し続けることです。特に大きな負担となるのが、リグレッションテストの実施です。既存機能が正常に動作することを確認するリグレッションテストは、バージョンアップのたびに全ケースを実行する必要があります。動作対象とするブラウザやデバイスごとにテストを実施する必要があるため、その工数は膨大なものになります。
SIに委託している場合でも、パッケージベンダーから機能追加や修正による影響範囲が十分に共有されることは少なく、SIが把握できる情報はユーザーと同程度にとどまります。そのため、バージョンアップ後のテストはユーザーが主体的に担わざるを得ず、SIは十分に関与できません。とはいえ、ユーザー側からは追加費用を投じてテストを依頼する判断材料も乏しいため、実務的にはテストが後回しになったり、限定的に実施される傾向が強まります。
こうした構造的なギャップは、テスト工程の省略や簡略化を招き、結果として品質リスクの増大につながります。万一不具合が残存したままリリースされれば、業務停止や修正コストの増加といった経営リスクに直結する可能性が高くなります。
テストケースの考慮漏れなどによる品質低下のリスク
パッケージ製品のバージョンアップ内容は、必ずしもすべての事項が明確に文書化されているとは限りません。内部的な処理の変更や、パフォーマンス改善のための実装変更など、ユーザーには見えない変更が含まれることが多く、これらが思わぬ不具合を引き起こす可能性があります。
また、テスト管理が不十分な場合、「誰が何を確認したか」「どのような結果だったか」といった情報が散在し、全体的な進捗状況や品質状態を把握することが困難になります。特に複数のチームが関わる大規模なテストでは、コミュニケーションの不足により重要な確認項目が漏れるリスクも考えられるでしょう。
そして、最も避けたい事態は、テスト不足により本番環境で不具合が発生し、エンドユーザーからの指摘で初めて問題に気付くことです。このような事態は、システムの品質に対する信頼を大きく損ない、ビジネスへの影響も甚大なものとなる可能性があります。
特に顧客向けサービスや基幹業務システムにおいては、わずかな不具合でも重大な結果を招く可能性があるため、確実なテスト実施が不可欠です。
スケジュールの圧迫
多くの企業において、パッケージ製品のバージョンアップ時期は期末や繁忙期と重なることが多く、通常業務との調整が大きな課題となります。
この期間中、テスト対応に追われることで、新規プロジェクトの進行が遅れたり、他の重要な業務改善活動が停滞したりする可能性があるため、注意が必要です。特に、IT部門の人員が限られている中小企業では、バージョンアップ対応が他のすべての活動を停止させる要因となることもあるでしょう。
対応が遅れることで連鎖的な影響が発生し、ビジネス機会の損失につながることも考えられます。そのため、迅速かつ効果的なテスト実施が必要です。
AIを活用して定期バージョンアップ対策を
定期バージョンアップに伴う課題を解決する有効な手段として、AI技術を活用したテスト自動化が注目されています。AI搭載のテスト自動化プラットフォームを導入することで、従来の手動テストでは実現困難だった効率的かつ網羅的なテスト実施が可能です。
Autifyを活用することで、パッケージ製品のバージョンアップに対して以下のような対策が実現できます。
- 更新のたびに自動テストを実施することで、影響範囲を即時に特定する
- AIがUIの変化を検知・追従し、テストを自動で作成する
- ノーコードで非エンジニアでもテスト作成・管理が可能になる
特筆すべきは、Autifyの提供する「Autify Nexus」は、Salesforceに標準で対応している、という点です。Salesforceは、パッケージ製品の中でも年3回という高頻度のサイクルでバージョンアップが実施されます。また、SAPを含む他の主要クラウド製品についても、画面操作を通じた自動テスト作成に活用できます。
カスタマイズ性の高い同製品のバージョンアップテストは非常に困難といわれてきましたが、Autify Nexusを活用することで継続的なテスト実施が可能となります。手動テストでは対応が困難だった網羅的な品質保証を実現できます。
まとめ
クラウド型のパッケージ製品は、機能向上とセキュリティ強化のために定期的なバージョンアップが実施されており、多くの企業がその都度、自社業務への影響を確認するためのテストに多大な工数を費やしているのが現状です。
AIを活用したテスト自動化の導入は、この課題に対する強力な解決策といえるでしょう。特にAutify Nexusのような自動化プラットフォームを導入することで、定期バージョンアップへの対応効率化だけでなく、日常的な品質保証活動全体の向上にも寄与します。
これにより、IT部門はより戦略的な活動に注力できるようになり、企業全体のデジタルトランスフォーメーションを加速させることにもつながっていきます。