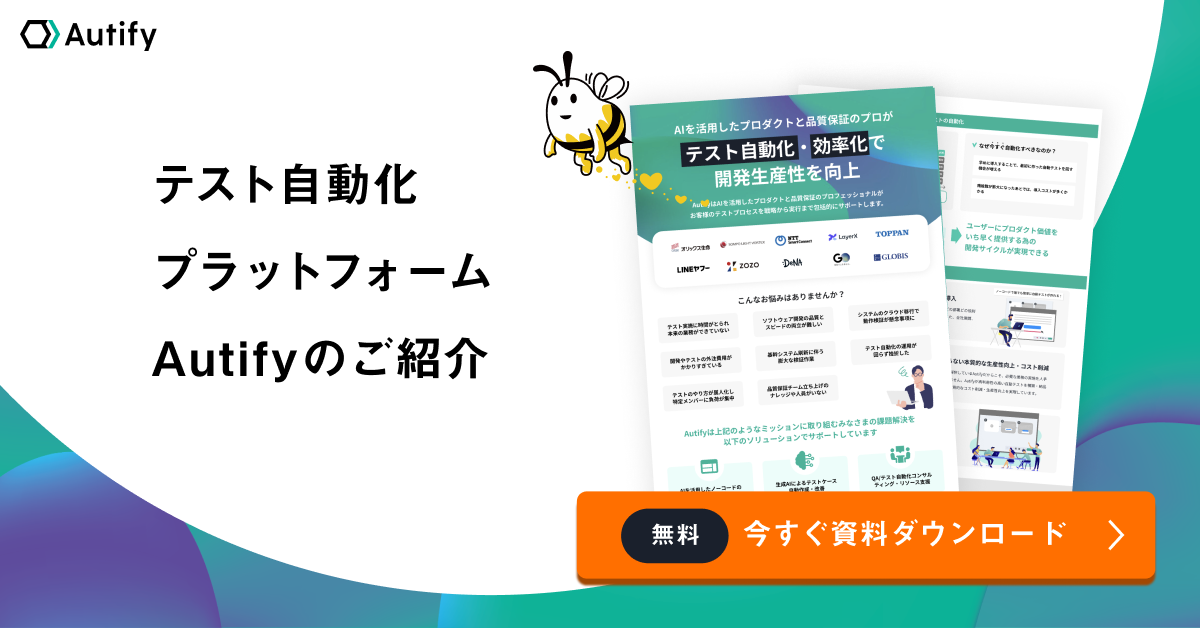ソフトウェアテストの工数削減に向けた効率化手法とすぐにできるアプローチ

ソフトウェアテストの工数はソフトウェアの規模や使用されている期間に比例して大きくなります。工数を削減するためには自動化やテストプロセスの見直し、などさまざまな対策がありますが、本記事では自動化に着目して、具体的な実践内容を解説します。
ソフトウェアテスト自動化を成功させる方法がわかれば、持続可能な工数削減を実現できるため、参考にしてください。
テスト工数がふくらむ3つの要因
テスト工数が膨らんでしまうのには以下の要因があります。
- 手動テストの限界
- テストケースの肥大化
- チーム間の連携不足
手動テストの限界
ソフトウェアテストを手動で行う場合、熟練した担当者や優れたツールがあっても実施回数や期間短縮には限界があります。
繰り返し作業やリグレッションテストを手動で実施すると、多くの時間と工数が必要です。また、担当者によってテストの精度やスピードに差が生じやすく、属人性が高くなる傾向があります。その結果、判断のばらつきによりテスト品質が損なわれることがあります。
さらに、限られた時間や予算の中で作業する必要がある中、手動テストでは作業ミスを完全に避けることは難しく、ミスが発生するとさらに工数が増大し、制約条件を満たせない場合もあります。
開発サイクルが短い現代では、手動テストだけでは対応しきれず工数が増大します。そのため、テスト自動化で限界を補い、効率的かつ安定した品質を確保することが求められます。
テストケースの肥大化
ソフトウェアは開発や機能追加が進むにつれて、テストケースが肥大化する傾向があります。
テストケースの肥大化とは、プロジェクトを重ねるごとにテストケースが増え、管理や実行のコストが大きくなる問題です。ソフトウェアの機能が充実するほど顧客満足度は向上しますが、それに伴いテストコストも増加します。機能が増えるとテストケースも増えることは容易に想像できるでしょう。
そのため、テスト設計の見直しや不要なテスト項目の削除を行わないと、実施するテストが過剰になり、効率が低下します。テストケースは定期的に見直し、肥大化に対応することが重要です。
さらに、AIを活用した自動化ツールを用いることで、テストケースの取捨選択や設計の自動化も可能です。テストの自動化だけでなく、設計段階から効率化を支援できるツールの導入が、肥大化対策に有効です。
チーム間の連携不足
ソフトウェアテストはチーム間の連携が不可欠ですが、連携が不足することでテスト工数の増大につながります。
円滑なソフトウェアテストを実現するためには、開発・テスト・運用などのチーム間の連携が必要です。これらの連携が取れていないと、手戻りや認識のズレが頻発します。特に仕様変更時、連携ミスはテストのやり直しを発生させ、無駄な工数を生む原因です。
例えば、開発チームによる機能追加の内容がテスト、運用チームに正しく連携されていなければ、テスト不足や運用時のトラブル対応が遅れてしまうなどの事態につながります。これらの事態は顧客の満足度低下やソフトウェアの信頼を失うことにつながるでしょう。
また、チーム内でも人数が増えればそれだけ連携不足の可能性が高くなります。可視化や綿密な連携、あるいはDevOpsによる迅速化で連携不足を防ぐ必要があります。
関連記事:DevOpsにおけるテストの自動化とは?導入方法やメリットを解説
テスト工数を削減する3つのアプローチ
テスト工数の削減は単なる作業量の削減ではなく、品質維持と効率性向上の両立ができる取り組みであるべきです。テスト工数を削減するアプローチとして以下が挙げられます。
- テスト自動化の導入
- テストプロセスの見直し
- 過去テストの再利用
テスト自動化の導入
テスト自動化を導入することで、テスト工数の削減が可能です。
繰り返し実施する単純作業や、大量のデータを扱うテストは、自動化によって大幅な工数削減が実現します。テストを自動化できるツールやスクリプトにテストを任せることで、手動作業のデメリットを減らすことが可能です。手動で行っていた作業の時間がかからないことはもちろんですが、誰がツールを動かしても同じ結果になることから、テスト品質も安定します。
また自動化ツールをCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)と連携すれば、コードの変更に応じて自動的にテストが実行される仕組みの構築も可能です。ソフトウェア側の更改が行われたら、その瞬間にテストが実行されることで、テストの準備や担当者間の連携にかかるコストも削減できます。
テスト自動化の仕組みを導入することで、テスト工数が膨らむ要因に対処が可能です。
テストプロセスの見直し
テストを行うまでのプロセスの見直しもテスト工数を削減するためのアプローチとして有効です。
テストプロセスには、要件定義から結合テストまでの流れがありますが、中には重複や過剰なテストもあります。これらを排除することでテスト工数の削減が可能です。特にテストの目的とリスクに応じた優先度付けができることで、重要な箇所にリソースを集中できます。
またテスト自体を開発プロセスの早い段階で実施することも有効です。これをシフトレフトと呼び、シフトレフトによって早い段階で方向性やプログラムを修正できることで、プロセス全体の工数削減につながります。
テストプロセスの順番や無駄がなくなれば、工数削減が可能なので定期的な見直しをしましょう。
過去テストの再利用
過去テストで使用したテストスクリプトや、テスト項目表、結果の再利用ができればテスト工数の削減ができます。
ゼロベースでテストプロセスを設計、実施することは簡単ではありません。2回目以降の同様の機能のテストや、仕様変更が少ない開発のテストであれば再利用できる部分がないか確認してみましょう。
ゼロベースで再実施するのではなく再利用時に内容を最新仕様に合わせて改訂するだけで、工数削減と品質の担保が可能です。よってテスト実施時は過去テストのデータとして管理、蓄積しておくことが重要になります。
テスト工数削減を成功させる3つのポイント
テスト工数を削減するには、単にツールを導入するだけでなく、正しい考え方と段階的な取り組みが必要です。以下のポイントを確認しておきましょう。
- 最初はマイナスだと理解する
- 自動化対象を絞る
- テストプロセスの見直しでPDCAを実践する
最初はマイナスだと理解する
テスト工数削減の取り組みは最初はマイナスからのスタートとなることを認識して始めましょう。
自動化やプロセス改善には初期投資や習熟の手間がかかり、短期的には工数が増えることもあります。これらの取り組みはPDCAサイクルによる改善を続けながら、時間をかけて成功につながるものです。
最初はマイナスであることを事前に理解しておき、中長期的な視点で取り組んでいくことがテスト工数の削減成功へのポイントになります。
自動化対象を絞る
自動化の対象を絞っておくこともテスト工数の削減成功に向けた重要なポイントです。
最初からすべてを自動化しようとすると、逆に開発・保守コストが増大します。自動化をする場合は工数が大きい、繰り返し実行される、など明らかに自動化に適している機能やプロセスに自動化対象を絞ることが重要です。
小さな自動化に成功したら、段階的に自動化対象を広げていくことで、自動化の効果を得つつ、さらなる自動化につなげられます。
また自動化自体を目的としないことも重要です。自動化の目的はあくまでテスト工数削減や品質向上に向けて行うべきであり、自動化はその手段にすぎないことを理解しましょう。
テストプロセスの見直しでPDCAを実践する
テスト工数削減に向けてテストプロセスを変更した場合は、定期的に振り返りPDCAサイクルにつなげましょう。
テスト工数を削減するには、見直したテストプロセスを定期的に振り返り、PDCAサイクルを通じて継続的に改善することが重要です。見直しによって時間をかけずに取り組むべきもの、あるいは時間をかけてでもテスト品質を優先するものに分類しましょう。分類後は、具体的な戦略を立てて改善につなげます。
例えば、結合テスト工程で不具合検出率が低い場合は、テストケースの一部を単体テストに移行し、早期にバグを発見できるようにします。この取り組みで、後工程での修正コストを抑えることが可能です。
テストプロセスを見直し、さらなる工数削減の策を練っていきましょう。
まとめ
ソフトウェアテストの工数は、さまざまな要因で膨らみやすいです。しかし、膨らみ続けたまま放置すると、品質低下や納期遅延のリスクが高まります。工数削減のためにはテストプロセスの見直しや自動化などの改善を実践すべきです。
Autifyは自動化対象を絞りつつ、自動化対象やテストプロセス見直しの提案ができるテスト自動化ツールです。AIを活用したこれらの機能により、工数削減の最初に生まれがちなマイナスが生まれにくい取り組みができます。