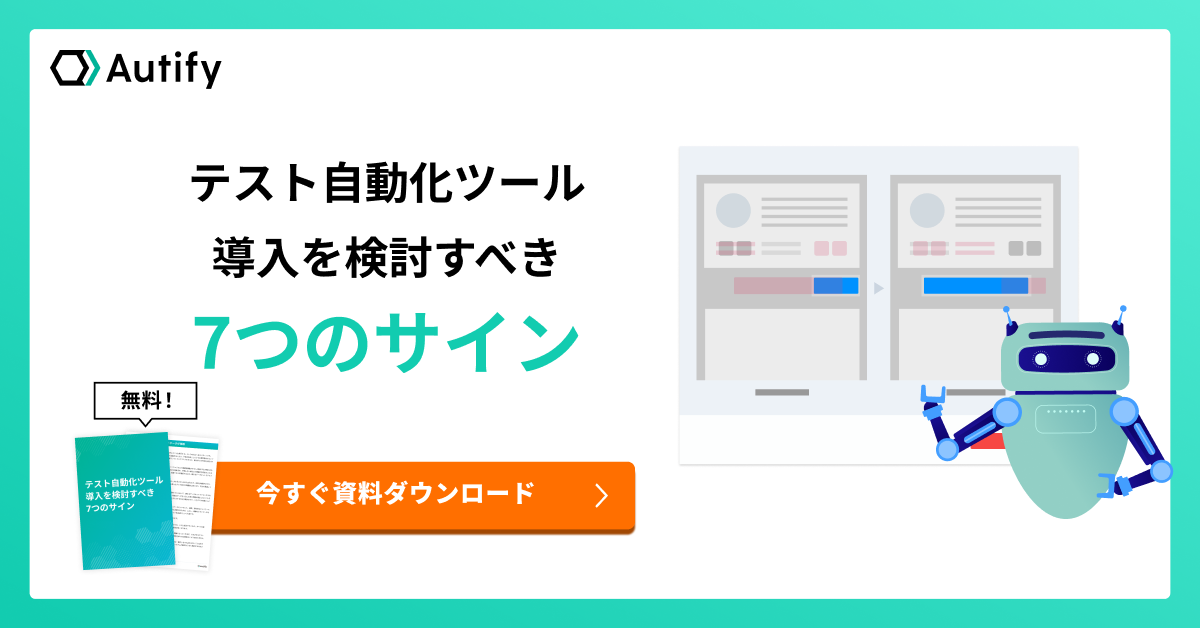テスト自動化とは?向き不向きの見極め方とAIで進化する最新ツール活用術

本記事ではテスト自動化の向き不向きやメリット、デメリットについて解説します。テスト自動化は明らかに向き不向きがあり、不向きなテストは実現できる可能性が低いばかりでなく、効果も薄くなる可能性があります。
AIの活用によるテスト自動化の最新事情も含めて確認していきましょう。
テスト自動化の基本
本記事で言及する「テスト自動化」とは、ソフトウェアテストの工程を自動化することを指します。
ソフトウェアテストは、開発したソフトウェアの品質を担保するために欠かせない取り組みです。しかし、手動で行う場合、多くの工数と時間がかかります。そこでテスト工程を自動化することで、「設計→開発→テスト→リリース」と続く開発サイクル全体のスピードを高めることが可能になります。
テスト自動化は、開発スピードの向上だけでなく、短期間での機能改善やバグ修正をしやすくする点でも、大きな効果を発揮します。
テスト自動化の目的と役割
テスト自動化の目的は、限られた時間と人員で品質を確保し、コスト削減と効率化を実現することにあります。自動化により、テストプロセスを迅速かつ一貫性を持って実行し、開発サイクルを迅速に進めることが可能です。
特に、アジャイル開発やDevOpsといった高速な開発サイクルが求められる現代において、テスト自動化はもはや「あれば便利」なものではなく、品質とスピードを両立するための「不可欠な戦略」となりつつあります。
なぜなら、昨今のビジネス環境においては、目的とするアプリケーションやサービスを予定通りにリリースすることが極めて重要です。 それにより、Time to Value(価値提供までの時間)の短縮、投資回収スピードの向上、収益性の改善、さらには顧客満足度の向上や他社との差別化といった、経営視点での重要な成果に直結します。
こうした状況下では、テストの自動化が果たす役割もますます大きくなっています。 単なる開発工程の効率化にとどまらず、持続的な事業成長を支える“基盤”としての役割を担うようになってきているのです。
この「事業成長の基盤」という役割を具体的に見ると、テスト自動化は、リグレッション確認をはじめとするさまざまなテスト活動を効率化し、システムの安定性や機能の正常な動作を継続的に確認する役割を果たします。これにより、開発サイクルの高速化と品質の維持・向上に貢献します。
ただし、テスト自動化には以下のよくある誤解があります。
- 自動化すればテスト工数が激減する
- 自動化することで品質が劇的に向上する
自動化をすればよい、というものではなく、目的を持ち正しい自動化をすることが重要です。
ソフトウェアテストに求められるもの
ソフトウェアテストには、限られたリソースや工数、期間の中で、製品の品質を確保することが求められます。これを実現するためには、人的リソースを投入すべきテスト項目を見極めると同時に、テスト自動化を適切に活用し、コストと時間の最適化を図る必要があります。
こうした制約の中で高品質なソフトウェアを提供するためには、綿密かつ実効性の高いテスト戦略の構築が欠かせません。自動化を効果的に組み合わせることで、重要なテスト項目を効率よく実施し、品質と開発スピードの両立を図ることが可能になります。
関連記事:ソフトウェアテストとは?AIが変える目的・種類と持続可能なコスト最適化
テスト自動化が求められている背景
開発手法の変化やシステムの複雑化、限られた開発リソース、そしてAI技術の進歩など、ソフトウェア開発にはさまざまな変化や制約がつきまといます。こうした環境の中で、テスト自動化が品質向上や開発サイクルの効率化に不可欠な理由として以下があります。
- 開発手法の変化
- システムの複雑化・高機能化・大規模化
- 限られた開発リソース
1.開発手法の変化
最近のソフトウェア開発は、伝統的なウォーターフォールモデルからアジャイル開発手法への移行が際立っています。
アジャイル開発の特徴は、迅速で短い開発サイクルを完遂できることです。昨今のシステムは仕様の変更が頻繁に発生するため、アジャイル開発により対応し、その都度テストの実施が求められます。テストの自動化によりアジャイル開発のサイクルにも素早く対応可能です。
2.システムの複雑化・高機能化・大規模化
現代のソフトウェアは急速に進化し、その結果、システムは過去の製品に比べて複雑で高機能かつ大規模化している状況です。
この複雑化と高機能化に伴い、テスト項目も増加の一途を辿っています。新たな機能や機能の組み合わせに対する確認が必要とされ、これが多岐にわたるテスト項目を生み出しています。
この状況に対応するためには、効率的で自動化されたテストプロセスの導入が重要です。自動化により、繰り返しのテストや多岐にわたるテスト項目の実施が容易になり、品質を確保する上での手間と時間を大幅な削減が実現します。
3.限られた開発リソース
開発リソースが限られている現場において、テスト自動化の重要性はますます高まっています。
テスト自動化は、限られた人員や時間、予算といったリソースを有効に活用する上で不可欠な手段です。繰り返し発生する手動テスト作業を自動化することで、開発者はより高度なタスクや開発業務に集中できるようになります。
限られたリソースの中で、効率的かつ確実にテストを実施するためにも、テスト自動化の導入は欠かせない取り組みといえるでしょう。
テスト自動化がもたらすメリット
テスト自動化にはさまざまなメリットがあります。本章では代表的な3つのメリットについて解説します。
- テストにかかるコストの削減
- 不具合・バグを早期に検知できる
- ヒューマンエラーによるテスト漏れのリスクを低減できる
1.テストにかかるコストの削減
繰り返し実施するテストケースを自動化することで、手動作業と比べて迅速かつ効率的なテストが可能になります。それにより、作業にかかる工数が大幅に削減され、結果としてテスト全体のコストも抑えられます。
このようにして生まれたコスト的な余裕は、プロジェクト内で他の品質向上活動や、新たなテストケースの作成といった領域にリソースを再配分することを可能にします。削減されたリソースを有効活用することで、より高度なテスト戦略の構築や、複雑なシナリオの検証にも注力できるようになります。
2.不具合・バグを早期に検知できる
テスト自動化の導入と適切なテスト実行により、不具合やバグを早期に検知できるというメリットがあります。開発が進行している最中でも、自動化したテストシナリオを定期的に実行できれば、潜在的な問題が素早く浮かび上がるでしょう。
開発チームは迅速かつ継続的にソフトウェアの品質を確認し、不具合が発生した場合には即座に修正に取り組めます。テスト自動化により早期の不具合検知ができれば、バグの影響が広がる前に対処できるため、開発サイクル全体の効率が向上します。
3.ヒューマンエラーによるテスト漏れのリスクを低減できる
テスト自動化を導入することで、ヒューマンエラーによるテスト漏れのリスクを大幅に低減できます。
手動テストでは、作業の繰り返しによって「いつも通りだから問題ない」といった思い込みが生まれやすくなり、チェック漏れや作業ミスにつながることがあります。自動化されたテストであれば、毎回確実かつ一貫した手順で実行されるため、人為的な見落としを最小限に抑えることが可能です。
このように、テスト自動化は人的ミスを防ぎ、重要な機能やシナリオの検証漏れを防止する上で大きな効果を発揮します。結果として、安定した品質管理体制の構築に貢献します。
テスト自動化のデメリット
テスト自動化はメリットばかりに感じますが、以下のデメリットも存在します。
- 初期費用がかかる
- メンテナンスが必要
- 自動化に向いていないテストもある
1.初期費用がかかる
テスト自動化の導入には、一定の初期費用が発生するというデメリットがあります。
テスト自動化は長期的には大きな効果をもたらしますが、導入初期の段階ではメリットを実感しづらいケースが少なくありません。主な初期コストとしては、以下のようなものが挙げられます。
- テスト自動化ツールの契約・購入費
- 自動化技術習得のためのトレーニングコスト
- 自動化スクリプトの作成にかかる人件費
さらに、自動化に不慣れなチームでは、テスト対象の選定や適切なツールの使い分けにも時間を要する可能性があります。
そのため、テスト自動化を導入する際は、目的や期待される成果をあらかじめ明確にし、「短期では効果が見えにくい」という点を理解した上で、長期的な視野を持って取り組むことが重要です。
初期段階では費用対効果が見劣りしやすいという点が、テスト自動化の導入における大きな課題の1つです。
2.メンテナンスが必要
テスト自動化には、メンテナンスにかかるコストが発生するというデメリットがあります。
自動化ツールは一度構築すれば終わりというものではなく、ソフトウェアやアプリケーションのアップデートに合わせて、テストスクリプトの見直しや修正が必要になります。メンテナンスを怠ると、既存のスクリプトが正しく動作しなくなったり、誤った結果を返したりするおそれがあります。
特にUIの変更やAPI仕様の更新が頻繁に発生するシステムでは、テストスクリプトの修正頻度も高くなり、初期投資の回収が難しくなるケースもあります。そのため、自動化されたテストケースについても、定期的なレビューと保守運用体制の整備が不可欠です。
テスト自動化によって削減できるはずの手動テスト工数が、メンテナンス作業として新たな工数を生むことを理解した上で、導入を検討する必要があります。
3.自動化に向いていないテストもある
すべてのテストが自動化に適しているわけではないことに注意が必要です。
例えば、新機能に対する探索的なテストや、手順が定まっていないテストは、自動化が難しいケースに該当します。自動化には工夫が求められ、場合によっては非効率となる可能性もあります。
特に、以下のようなテストは自動化に不向きです。
- 人の目線が重要なテスト
ユーザーの感覚や主観的な判断が求められるため、自動化では対応が困難です。
例:ユーザビリティテスト、アクセシビリティテスト - 実行のたびに結果が変わるテスト
環境や外部要因に依存し、再現性が安定しないため、自動化に適しません。
例:他のテストの実行順序に依存するテスト、時刻や外部データソースに依存するテスト
このようなケースでは、自動化よりも人の手による確認や、柔軟なテスト設計に注力すべきです。
したがって、自動化はすべてのテストに一律で適用するのではなく、適した対象に絞って導入を進める必要があります。
なお、自動化に向いているテストの具体例については、後述します。
自動化に向いているテスト
テスト自動化はテストの特徴によって向き不向きがあります。自動化に向いている特徴として以下があります。
- 繰り返し作業が多いテスト
- 操作項目や手順が明確に定まっているテスト
- 人間による実施が困難な複雑なテスト
- 頻繁に実施するテスト
繰り返し作業が多いテスト
繰り返し作業が多いテストは、自動化に適した代表的なケースの1つです。
人間が同じ操作を何度も繰り返すと、疲労や集中力の低下によってミスが発生しやすくなります。一方で、自動化されたスクリプトであれば、常に一定の手順と品質でテストを実施できます。
例えば、入力フォームのバリデーションチェックや、ログイン後の画面遷移確認といった、定型的かつ繰り返し頻度の高いテストは、自動化の効果が特に高い領域です。
このような繰り返し作業を自動化することで、人的リソースの負担を軽減し、より高度なテストや開発業務に集中できる環境を整えることができます。
操作項目や手順が明確に定まっているテスト
操作項目や手順が明確に定義されているテストは、自動化に適した典型的なケースです。
自動化スクリプトは、あらかじめ定義された操作手順や比較条件に基づいて処理を実行するため、経験的な対応が求められるテストには不向きです。その一方で、手順が明確であるほど、スクリプトが安定して動作し、再現性の高いテスト結果を得ることができます。
例えば、決済処理の一連のフローや、画面遷移に伴う特定メッセージの表示確認などは、ルールが明確であれば、自動化による検証が十分に可能です。
このように、人間の判断を必要とせず、操作と期待結果が明確に定まっているテストは、自動化による恩恵が大きく、導入効果が得やすい領域といえるでしょう。
人間による実施が困難な複雑なテスト
人間が手作業で実施するには難しく、ミスが起こりやすいテストは、自動化に適したテストの代表例です。
手順が複雑であったり、入力パターンが多岐にわたるためにミスが発生しやすいテストケースは、人間にとって負担が大きいものの、機械にとっては正確かつ迅速に処理できるため、自動化による効率化が特に効果的です。
具体例としては、大量のパラメータを使って機能の境界値を検証するような、入力ミスや見落としのリスクが高いテストが挙げられます。
さらに、自動化によりスクリプトの事前レビューを複数人で行ったり、実行結果を自動で記録したりできるため、テストの再現性やトレーサビリティの向上にもつながります。
頻繁に実施するテスト
頻繁に実施するテストも、自動化に最も適したテストの1つです。
ビルドやデプロイのたびに必ず実行しなければならないテストは、自動化することで大きな効果を発揮します。特にリグレッションテストは、自動化による効率化効果が非常に高い代表的な領域です。
手動で何度も繰り返し行う頻度の高いテストは、開発チームに大きな負担となり、場合によってはテスト自体が形骸化してしまうリスクもあります。自動化を導入することで、テスト漏れや実施忘れを防止できるため、品質維持に寄与します。
また、自動化したテストは回数を重ねるほど効果が高まり、長期的なコスト削減と品質向上につながります。頻繁に実施するテストは積極的に自動化を進めるべきでしょう。
自動化に向いていないテスト
逆に自動化に向いていないテストの特徴として以下があります。
- 実行回数が少ないテスト
- 人間の感覚や判断が必要なテスト
- 仕様変更が頻繁な機能のテスト
- ユーザー認証が必要なテスト
実行回数が少ないテスト
実行回数が少ないテストは、自動化にあまり適していません。
その理由は、自動化の効果が限定的だからです。テスト自動化は繰り返し実行することでコスト削減や効率化の効果を発揮します。一方で、一度きりの実行や年に数回程度しか行わないテストでは、導入にかかるコストを回収できない可能性が高いです。
具体例としては、半年に一度、手動で30分程度かけて実施する機能確認テストなどが挙げられます。こうした実行頻度が低く、短時間で完了するテストは、手動で行うことが合理的だといえるでしょう。
人間の感覚や判断が必要なテスト
人間の感覚や判断が必要なテストも自動化に向いていません。
プログラムによる結果の判別が難しいテストは、現在の技術では自動化できないためです。直感的な使いやすさや、デザインのバランスなど数値化やプログラムによる判断ができない処理は自動化ができません。
例えば「このボタンは押したくなるか」「配色が見やすいか」「説明がわかりやすいか」などの観点は、人間の主観や感覚が判断の基準です。
これらは現状ではテスト自動化ができないため、手動のチェックが必要です。
仕様変更が頻繁な機能のテスト
仕様変更が頻繁に行われる機能のテストも自動化には向いていません。
理由は自動化をしても、すぐにその自動化が通用しなくなってしまうためです。仕様変更や画面構成の変更が頻繁に発生する機能は、変更のたびに自動化スクリプトを更新する必要があります。自動化ツールのメンテナンス負担が大きく、場合によっては修正にかかる手間が手動テストよりも大きい場合も出てくるでしょう。
こうしたケースでは、まず仕様を安定させてから自動化を進めるとよいでしょう。
ユーザー認証が必要なテスト
ユーザー認証が必要なテストは、自動化との相性があまり良くない傾向にあります。
サービスによっては、セキュリティ上の理由から自動化ツールによるログイン操作を制限している場合があります。例えば、CAPTCHAや多要素認証など、人間による操作を前提とした仕組みが導入されている場合は、自動化が意図的に困難に設定されています。
さらに、セキュリティポリシーによって、テスト環境で本番と同じ認証情報の使用が禁止されているケースもあります。その場合、自動化スクリプトに認証情報を組み込むことができず、ログイン処理の自動化が制限されるため、現実的には対応が難しくなります。
このような条件下では、ユーザー認証を含むテストは手動で実施するのが現実的かつ安全な選択肢といえるでしょう。
テスト自動化ツールの種類
テスト自動化を実現するためには、ツールの選定とその後の開発作業が必要です。
違いを一言で述べると、プログラミングをして自社でツールを作る形と、プログラミングが不要なテスト自動化ツールを用意してそこで開発を進める形です。
フルスクラッチ(プログラミングによる開発)
フルスクラッチ型は、プログラミングにより自動化ツールを作成する方式です。
プログラミングの際にはSeleniumやPlaywright、Cypressなどのフレームワークを活用し自動化を実現します。
この手法のメリットは、きめ細かい制御が可能な点です。複雑な条件分岐や例外処理、外部サービスとの連携、認証情報の取り扱いなど、柔軟なテスト設計ができます。実行環境や検証条件が複雑な大規模プロジェクトでも、細かい仕様に対応した自動化が実現可能です。
一方で、プログラミングのスキルが求められるため、導入のハードルが高いデメリットがあります。スクリプトの作成やメンテナンスをエンジニアや外部リソースに頼る必要があるため、開発・保守コストが大きくなります。
フルスクラッチはきめ細かい自動化を実現したい場合に採用すべき自動化手法といえます。
ローコードやノーコード
プログラミングをあまりしなくてもテスト自動化ができる、ローコードやノーコードのツールを使う手法です。
ローコード・ノーコード型のテスト自動化ツールは、プログラミングの知識がなくてもテストシナリオを作成・実行できるよう設計されています。代表的なツールは、Autify、Ranorex、Katalonなどです。
これらは、GUIベースの操作によってテスト自動化が可能な点がメリットです。テストの記録・再生機能やテンプレートを活用して手軽に自動化もできます。
よって開発チームにエンジニアが少ない場合や、テスト担当者が非エンジニアである場合でも導入しやすい点が魅力です。ただし、細かい制御や特殊なシナリオへの対応が難しいデメリットがあります。
ローコードやノーコードは柔軟性よりも手軽さやスピードを重視するプロジェクトに向いている自動化手法です。
テスト自動化ツール選定のポイント
前章ではテスト自動化ツールの種類を解説しましたが、ツール選定には以下のポイントがあります。
- 導入・学習の容易さ
- メンテナンス性・拡張性
- 対象範囲と機能の網羅性
- CI/CD連携と開発サイクルへの統合のしやすさ
- サポート体制と将来性
なお「プロジェクトで扱うプログラミング言語やOSに対応しているものの中から選ぶ」ことを選定の前提とします。
導入・学習の容易さ
自動化ツールの導入や学習が容易かどうかが選定ポイントの1つです。
まず自動化ツールは、導入後すぐに運用できることが重要です。すぐに運用できるためには、専門知識がなくても使いやすいUIや操作性が求められます。特に開発チーム以外のメンバー(QA担当者や業務部門など)もテストに関わる場合、ツールの直感的なUIやガイド機能が重要です。
ノーコード・ローコードでテスト作成が可能なツールであれば、エンジニアでなくてもテスト自動化を始められ、現場全体での品質管理がしやすくなります。
メンテナンス性・拡張性
テスト自動化ツールを選定する際には、メンテナンス性や拡張性の高さも重要なポイントとなります。
自動化は「一度構築して終わり」ではなく、UIの変更や仕様の更新に応じて、テストスクリプトの修正を継続的に行う必要があります。メンテナンス性が低いツールを選んでしまうと、そのたびに工数がかかり、結果として運用コストがかえって増加してしまうリスクがあります。
さらに、将来的にテスト対象が増加した際に柔軟に対応できる拡張性も不可欠です。規模が大きくなるほど、管理・運用のしやすさが品質維持に直結します。
AIによる自動修復機能を備えたツールや、スケーラブルな構成に対応できる仕組みを持つツールは、こうした課題への対応力が高く、選定において有力な選択肢となるでしょう。
対象範囲と機能の網羅性
導入するツールが対象範囲と機能の網羅性があることも重要です。
ツールを選ぶ際には、自社のテスト対象や用途に対応できるかを確認する必要があります。Webアプリケーションだけでなく、モバイルアプリ、APIテスト、E2Eテスト、リグレッションテストなど、さまざまなシナリオに対応できることが理想です。
Autifyは多端末テストやGenesisによるテスト設計支援など幅広いテスト領域への自動化支援ができます。
テストの必要な機能が揃っていることが選定ポイントとして欠かせません。
CI/CD連携と開発サイクルへの統合のしやすさ
CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)連携と開発サイクルへの統合に統合しやすいことも選定基準とすべきです。
近年の開発現場では、DevOpsやCI/CDが一般的になっています。JenkinsやGitHub ActionsなどのCI/CDツールと連携し、ビルドやデプロイのたびに自動でテストが実行できると、品質向上と開発スピードの両立が可能です。
開発サイクル全体の効率化につながるツールが望ましいです。
サポート体制と将来性
ツール導入後のサポート体制や将来性が高いことも選定基準になります。
トラブルが発生したときに、迅速かつ的確にサポートを受けられるかどうかで、スムーズな運用に直結します。スムーズな運用がバグ検出・修正を早めることになります。
またツール自体が継続的にアップデートされ、ユーザーの要望に応じた機能追加や改善が行われているかが将来性の判断材料です。将来性が高いツールほど、長期間に渡って活用でき、効果も大きくなります。
非機能部分にも注目した選定を行いましょう。
テスト自動化を成功に導く5ステップ
テスト自動化を成功させるには以下の5ステップが重要です。
- 自動化の目的を決める
- テスト自動化ツールの選定を実施
- テストケースを自動化する
- テストを実施する
- 振り返りを行う
ステップ1:自動化の目的を決める
なぜテスト自動化を導入したいのか、目的を明確にしておきましょう。
テスト自動化の目的が曖昧なままでは、導入後に思ったような成果が得られず、形骸化するリスクがあります。自動化自体が目的になってはいけません。
「どのような試験(単体、結合、E2Eなど)」「どのようなテスト項目(リグレッション、UI確認など)」を「どのような手段で」自動化したいのか、関係者間で意識合わせすることから始めましょう。
ステップ2:テスト自動化ツールの選定を実施
自動化の目的が決まったら、次はそれを実現できるツールを選定します。
まずはフルスクラッチか、ローコード・ノーコードツールを導入するのかを決めます。先述した「使いやすさ」「メンテナンス性」「対象範囲」「CI/CD連携」「サポート体制」の選定ポイントを総合的に評価することが重要です。
例えば、エンジニア以外が多いプロジェクトなら、ノーコード・ローコード型のツールが適しています。一方、カスタマイズ性を重視するならフルスクラッチやスクリプトベースがおすすめです。
ステップ3:テストケースを自動化する
選定したツールを使って、いよいよテストケースの自動化を行うステップです。
ただし、すぐに本番運用するのではなく、まずは小さな範囲で自動化ツールを試験的に導入し、予行演習をしてみましょう。
演習の結果「どこまで自動化するか」の線引きも重要です。また運用開始直後はすべてのテストにツールを適用することが難しいケースがあるため、効果の高い領域から段階的に導入を進めていく方針が現実的です。
ステップ4:テストを実施する
自動化されたテストを、実際の開発サイクルに組み込み、運用へと移行するステップです。
手動テストから置き換えることで、自動化の効果を実感できます。
ステップでは、テスト結果の記録やレポート出力など、成果の確認も重要です。自動化テストが開発や品質向上にどのように貢献しているかを定量的に示せると、今後の自動化につながりやすくなります。
ステップ5:振り返りを行う
テスト自動化ツールの運用後は定期的な振り返りが重要です。
「どのテストが効果的だったか」「保守コストはどうか」「手動テストは減ったか」などの観点で評価を行いましょう。
振り返りの結果をもとに、新たに自動化すべき領域や、運用改善のヒントを抽出することも可能です。ツールの活用方法を見直したり、自動化対象を段階的に拡大したりと、継続的な改善サイクルを回すことが成功の鍵となります。
AIを活用した次世代のテスト自動化の可能性
昨今話題に上がるAIはテスト自動化にも活用が可能です。活用により、テスト自動化のデメリットの低減や自動化に向かないテストに対しての活路を見出せる可能性が出てきます。
以下で、AIを活用したテスト自動化のメリットとして以下4点を解説します。
- テストケースの作成自動化
- メンテナンスの容易さ
- テスターと共に成長
- 導入ハードルの低さ
テストケースの作成自動化
AIを活用することで、テストケース作成の自動化が可能です。
一般的に「テスト自動化」と聞くと、多くの人が「実行工程の自動化」を思い浮かべがちです。本記事でも、これまではテストケースや手順書を手動で作成し、その実行部分を自動化する手法を中心に紹介してきました。
しかし、実行前のテスト設計にも多くの工数とコストがかかるのが現実です。そこにAIを活用すれば、テスト作成の初期段階から自動化を実現でき、大幅なコスト削減につながります。
例えば、AIが仕様書や画面設計書を解析し、主要な利用シナリオを抽出した上で、最適なテストケースを自動生成するといった流れが実現可能です。さらに、生成されたテストケースは、そのまま自動実行へと連携させることもできます。
AIの活用によって、テストの「実行」だけでなく「設計」までを自動化することで、コストの最適化や属人化の防止、品質向上にも貢献できるでしょう。
メンテナンスの容易さ
AIを活用するとテスト自動化ツールのメンテナンスも容易になります。
テスト自動化のデメリットとして、UI変更や仕様変更に伴う「メンテナンスの負荷」を解説しました。基本的にメンテナンス時には手動でスクリプトの修正が必要でしたが、AIの導入によりその課題も解消できます。
例えば、AIが実行結果を分析し、失敗の原因を特定した上で「どのテストを、どのように修正すればよいか」の提案が可能です。
AIの活用により、テスト自動化後のメンテナンス工数を抑え、実施すべき開発業務やテスト業務にリソースを集中できます。
テスターと共に成長
AIによるテスト自動化は担当者であるテスターと共に成長し、内製化を進めやすいこともメリットです。
テスト自動化を実現した場合、テストやサービスの内容を理解しなくてもテストができるため、人材育成が疎かになってしまう課題があります。しかし、AIは単なる代替手段ではなく、テスターの成長を支援するパートナーとして活用可能です。
例えば、AIがテストケースの構造や最適化方法をリアルタイムでフィードバックし、テスター自身がより高度なスキルを身につけられます。
AIの活用でテスト自動化の運用を内製化し、自動化ツールの精度向上とテスターの成長という相乗効果を期待できます。
またAutifyの自走支援型のサービスでは「自動化は進めたいが、人も育てたい」という悩みの解決も可能です。
導入ハードルの低さ
AIの活用により、テスト自動化の導入ハードルを下げるメリットがあります。
従来のテスト自動化は、ローコード・ノーコードであっても一定のスキルや時間を要することがネックでした。しかしAIの活用により、このハードルも大きく下がっています。
例えばフルスクラッチ開発が必要な場合でも、AIがソースコードの雛形を提案してくれるため、実装の負担を軽減可能です。またローコード・ノーコードであっても、提案が可能であり、細かい実装を実現しやすくなります。
AIの力により、自動化初心者のチームでもスムーズに自動化ツールを導入・運用を開始できます。
まとめ
テスト自動化は開発サイクルを早め、短期間での改良やバグ修正がしやすさ向上に貢献する取り組みです。自動化は必須ではなかったものの、昨今のビジネス状況の変化や開発サイクルの迅速化に伴って、必須といえる状況になってきました。
テスト自動化にはさまざまなメリットがありますが、デメリットや向き不向きを理解して取り組む必要があります。そしてAutifyのテスト自動化ツールはAIを組み込んでおり、デメリットや不向きなポイントの低減が可能です。
Autifyはソフトウェアテストの支援、生成AIを用いた自動化のサポートなどさまざまな支援をさせていただきます。テスト品質、短納期への対応、自動化にお困りの際はぜひこちらまでご相談ください。