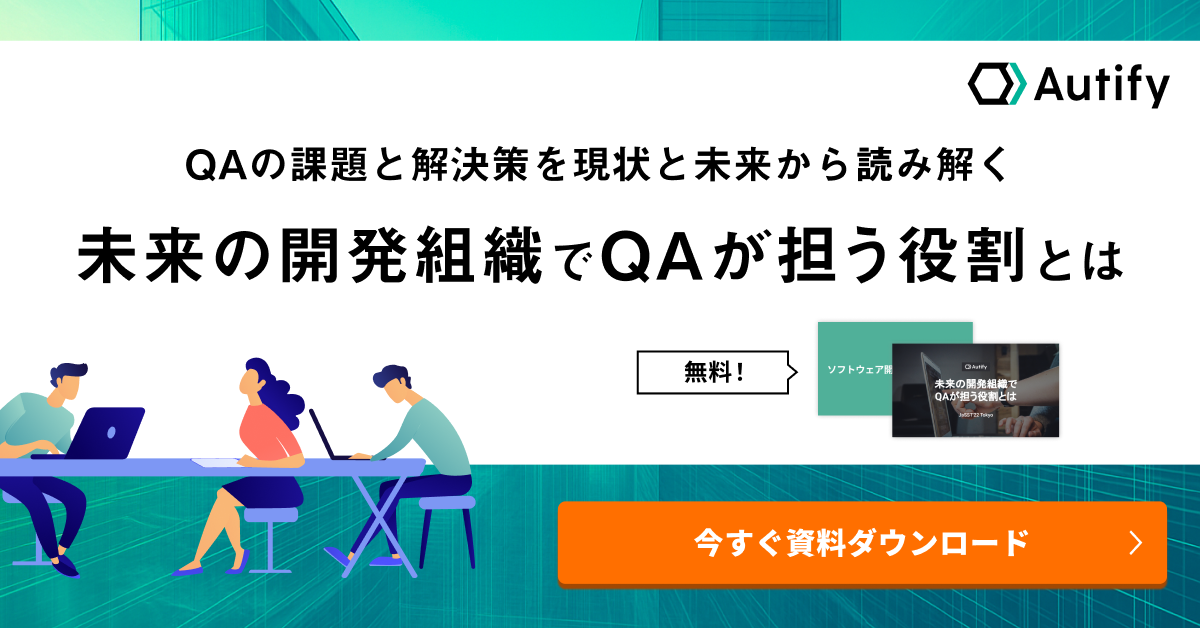品質保証(QA)と品質管理(QC)の違いとは?課題と改善手法を徹底解説

「品質保証」と聞くと、製造業の工場やライン検査をイメージする人も少なくありません。しかし現代では、ソフトウェアの分野でも品質保証(QA)や品質管理(QC)の重要性が高まっています。本記事では、ソフトウェア開発における品質保証・品質管理の基本的な考え方や実践的な取り組みについて、製造業でも活用されている分析やフレームワークにも触れながら、わかりやすく解説します。
品質保証(QA)・品質管理(QC)とは?基本的な概念
品質保証(Quality Assurance:QA)は、製品・サービスが期待される品質を安定的に満たすための仕組みや活動を指します。もともとは製造業で培われた概念ですが、ソフトウェアでは形のない製品を対象に、迅速かつ柔軟な品質対応が求められるという特有の事情があります。そのため、品質保証・品質管理(Quality Control:QC)の考え方やアプローチも、ソフトウェア開発に最適化された形へと進化してきています。
ここでは、品質の基本的な考え方と、品質保証および品質管理の定義と役割について解説します。
ソフトウェアにおける品質とは何か?
ソフトウェアにおける「品質」とは、単にバグがない状態だけを指すのではありません。ユーザーの期待に応える使いやすさや安定性、パフォーマンスなどを総合的に備えているかが重要です。
近年では、利便性や保守性、セキュリティといった観点も品質の一部として重視されています。こうした要素を開発や運用の各段階で適切につくり込むことが、顧客満足度やサービスの信頼性向上につながるのです。
市場の変化に柔軟に対応できることも、現代の品質に欠かせない要素でしょう。
品質保証(QA)の定義と目的
品質保証(Quality Assurance:QA)とは、製品・サービスがあらかじめ定められた品質要求を安定して満たせるように、設計から製造、運用までの各工程を体系的に管理する活動です。
目的は、不良やトラブルの「発生を未然に防ぐ」ことであり、品質問題の早期発見や再発防止に向けた仕組みづくりが中心となります。検査のように「完成品を確認する」手段とは異なり、品質保証はプロセス全体に関与し、品質をつくり込む文化や体制の構築にも深く関わっているのが特徴です。
企業においては、信頼性やブランド価値を支える基盤ともいえるでしょう。
品質管理(QC)の定義と役割
品質管理(Quality Control:QC)とは、製品やサービスが設定された品質基準に適合しているかを確認し、品質の安定を図るための活動です。
主に検査や測定、工程の分析を通じて不適合の原因を把握し、是正措置を講じる役割を担います。品質管理は「できあがったものをチェックする」点に重点が置かれがちですが、近年では工程そのものを見直す改善活動としても重視されるようになりました。
品質保証が全体の仕組みをつくる活動であるのに対し、品質管理はその仕組みを運用し、品質の維持・管理を実現する手段だといえるでしょう。
品質保証(QA)と品質管理(QC)の違い
品質保証と品質管理は、品質を維持・向上させるために不可欠な活動ですが、役割や対象とする領域が異なります。ここでは、それぞれの違いや補完関係、そして連携による相乗効果について解説します。
品質保証(QA)はプロセス中心、品質管理(QC)は結果中心
品質保証は、設計や開発、製造などのプロセス全体に目を向け、計画段階から品質をつくり込むことを目的としています。
対して、品質管理は製品・サービスの最終的な成果物が基準を満たしているかを検証し、不具合の是正を行うという結果重視のアプローチです。
言い換えれば、品質保証は「不良を出さない仕組みづくり」、品質管理は「出てきた不良を見つけ、改善する活動」であり、両者は補完的に機能する関係といえるでしょう。
なぜ「2個1」の存在と呼ばれるのか
品質保証と品質管理は、それぞれ異なる視点から品質にアプローチするものの、どちらか一方だけでは十分な成果を得ることは困難です。
品質保証が不具合の予防を主眼に、工程全体を整える仕組みであるのに対し、品質管理は実際の成果物をチェックし、問題の兆候を見つけて改善につなげる実務的な活動です。
このように、予防と検出、計画と実行という形で補完し合うため、両者は「2個1(にこいち)」の関係と呼ばれ、品質管理体制における両輪として機能しています。
品質保証(QA)/品質管理(QC)連携による品質向上
品質保証と品質管理は、互いに補完しながら組織全体の品質向上を支える存在です。例えば、品質管理で得られた検査結果や不具合情報を品質保証において分析し、次の製品設計や工程改善に反映することで、不具合の未然防止につながります。
逆に、品質保証で策定した品質基準や工程管理手順が、品質管理の検査活動の効率や精度を高める役割を果たすこともあります。このような情報の循環とフィードバックがうまく機能すれば、品質トラブルの再発防止やプロセスの継続的改善が可能となり、組織全体での品質向上が実現されるのです。
品質保証(QA)と品質管理(QC)の開発プロセスごとの業務内容
品質保証と品質管理の役割は、製品・サービスのライフサイクルごとに変化します。各開発フェーズにおいて、どのような業務が求められるのかを段階ごとに整理し、その特徴を見ていきましょう。
要件定義・設計フェーズでの品質保証(QA)の役割
品質保証は、開発の初期段階から関与することで品質を根本からつくり込む役割を果たします。特に要件定義・設計フェーズでは、ユーザーのニーズや業務要件を的確に反映させることが求められ、ここでの認識のズレが後の不具合につながることも少なくありません。
品質保証担当者は仕様の妥当性を確認し、リスクを事前に洗い出すことで、後工程での手戻りを減らせます。初期段階からの品質意識の共有は、全体の効率と成果物の完成度を大きく左右する重要なポイントです。
構築・テストフェーズでの品質保証(QA)/品質管理(QC)活動
構築・テストフェーズでは、品質保証と品質管理の双方が現場レベルで活発に機能します。
品質保証は設計通りに実装されているか、品質基準が守られているかをチェックし、レビューやガイドラインの運用を通じて品質リスクを低減します。一方、品質管理は完成した機能や製品・サービスに対し、実際の動作検証や不具合の検出・分析を行うのが役割です。
両者が密に連携し、設計と実装のギャップを早期に把握することで、重大な不具合の発生を未然に防ぐ体制が築かれます。
リリース後の品質保証(QA)と継続的な品質管理(QC)
製品・サービスがリリースされた後も、品質保証と品質管理の取り組みは終わりません。
品質保証は、ユーザーからのフィードバックや市場からのクレーム情報を収集・分析し、次の改善に向けた計画立案に関与します。一方、品質管理は運用中のトラブル対応や定期的な品質評価、再発防止策の実施を担い、安定稼働を支える役割を果たします。
特に近年では、サブスクリプション型サービスの普及により、リリース後も継続的に品質を見直す体制が求められています。
品質保証(QA)・品質管理(QC)を支える効果的な手法と考え方
品質保証や品質管理をより実効的に機能させるには、現代的な手法やマインドセットの導入が欠かせません。ここでは、代表的な考え方と手法について実践的な視点で紹介します。
シフトレフトによる早期品質保証(QA)の重要性
シフトレフトとは、品質保証の取り組みを開発プロセスの初期段階へ移行する考え方です。要件定義・設計フェーズから品質に目を向けることで、仕様の曖昧さや潜在的なリスクを早期に検知し、手戻りのコストを大幅に削減できます。
従来はテスト工程で見つかっていた不具合も、シフトレフトによって前倒しで対処できるため、全体の開発効率が向上する点も大きな利点です。
また、開発チーム全体が品質意識を共有しやすくなり、品質保証が「後工程の守り」から「全体の支援役」へと進化する契機にもなるでしょう。
リスクベースドテストと探索的テスト
リスクベースドテストは、発生頻度や影響度が高いリスクに優先的に対応するテスト手法です。限られたリソースの中でも、重要度の高い箇所を重点的に検証できるため、効率的かつ戦略的な品質確保が可能になります。
一方、探索的テストは、事前にテストケースを固定せず、テスターの直感や経験をもとに柔軟に実行する手法です。仕様の曖昧な部分や予期せぬ動作が起こりやすい場面において特に効果を発揮します。
これらの手法は、定型的な検証を補完し、より深く実践的な品質評価を実現する上で有効といえるでしょう。
品質保証(QA)とDevOpsの融合
DevOpsは開発(Development)と運用(Operations)を連携させるアプローチですが、そこに品質保証を組み込むことで、継続的な品質改善が可能です。
品質保証がDevOpsのパイプラインに統合されることで、コードの変更が即座にテストされ、不具合の早期検出と迅速なフィードバックが実現します。これにより、リリースのスピードと品質の両立が可能となり、チーム全体で品質責任を共有する文化の醸成にもつながります。
自動化やCI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)の活用と併せて実践することで、現代の開発体制に適した持続可能な品質保証が実現可能です。
品質管理(QC)・分析に役立つ代表的フレームワーク
品質管理を実践する上で欠かせないのが、課題の見える化と改善を支えるフレームワークや分析手法です。ここでは、現場で広く活用されている基本ツールや概念を紹介します。
品質管理(QC)の「7つ道具」
製造業や品質管理の現場で長年活用されてきた「7つ道具」は、課題の可視化と分析に役立つ基本的なフレームワークです。
グラフ
グラフはデータの傾向や変化を視覚的に把握するための基本ツールであり、品質管理の現場でも頻繁に用いられます。折れ線グラフや棒グラフを使えば、工程ごとの進捗や不良率の推移を一目で把握でき、問題の早期発見に役立ちます。
データの比較や分析を円滑に行う上で、最も身近で汎用性の高い表現手段といえるでしょう。
ヒストグラム
ヒストグラムは、データの分布やばらつきを視覚的に確認するための棒グラフ形式の図です。例えば、製品のサイズや処理時間といった連続する数値データを分類し、その頻度を表示することで、工程の安定性や異常の兆候を把握できます。
品質のばらつきに着目するQC活動では、工程能力の評価や改善箇所の特定に非常に有効です。
管理図
管理図は、工程の安定性を時系列で確認するための統計的手法です。
測定値を時系列に並べ、上限・下限の管理線を設定することで、工程が正常範囲内で推移しているかを判断できます。
突発的な変動や傾向の変化を即座に把握できるため、異常の早期発見と迅速な対処が可能です。安定した品質維持のために、日常的に活用される基本ツールです。
パレート図
パレート図は、不良要因や問題の発生頻度を項目別に分類し、重要度の高い順に棒グラフで可視化する手法です。横軸に項目、縦軸に件数を取り、累積比率線を加えることで「80対20の法則」に基づいた重点管理が可能になります。
限られたリソースで効果的な改善を行うために、真のボトルネックを特定するための有力な分析ツールです。
散布図
散布図は、2つの要素間の関係性を視覚的に捉えるための図です。
縦軸と横軸に異なるデータを取り、それぞれの測定値を点で表すことで、相関関係の有無や傾向を把握できます。
例えば「温度と不良率」や「作業時間と生産数」など、原因と結果の関連性を探る場面で活用されます。仮説検証や改善の糸口を見つけるために有効な手法です。
特性要因図
特性要因図は、「なぜその問題が起きたのか」を構造的に整理するための図で、魚の骨に似た形から「フィッシュボーン図」とも呼ばれます。問題(特性)に対して、その原因(要因)を人・設備・方法・材料などのカテゴリで分類し、関係性を明確にします。
複数の要因が絡む複雑な不具合の根本原因を探る場面で非常に有効なツールです。
チェックシート
チェックシートは、特定の項目についての記録や確認を行うための定型フォーマットです。作業中のミス防止や不良発生の傾向分析などに活用され、現場での記録精度や作業標準化を高める効果があります。
記入の手間が少なく、誰でも扱いやすいことから、品質管理の入門ツールとしても広く用いられています。蓄積されたデータは、後の改善活動にも役立ちます。
PDCA
PDCAは、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の4段階からなる継続的改善のサイクルで、品質管理の基本フレームワークとして広く知られています。
まず目標と計画を立て(Plan)、それを実行(Do)し、結果を検証(Check)した上で、改善措置を講じて次の計画に反映させます(Act)。
このサイクルを回し続けることで、業務の質や効率が徐々に高まっていきます。
シンプルながらも、実践の積み重ねによって大きな成果を生む手法です。
5S
5Sは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つの頭文字を取った職場改善の基本原則です。
不要なものを捨てる(整理)、使いやすく配置する(整頓)、常にきれいに保つ(清掃)、衛生的な環境を維持する(清潔)、そしてこれらを習慣化する(しつけ)という一連の活動により、作業効率や安全性が向上します。
製造業を中心に広まりましたが、オフィスやソフトウェア開発現場でも活用され、品質を支える土台づくりとして注目されています。
TQM
TQM(Total Quality Management)は「全社的品質管理」と訳され、部署や役職を問わず、組織全体で品質向上に取り組むマネジメント手法です。
品質は一部門だけでなく、全社員の意識と行動により築かれるという考え方に基づき、顧客満足度の最大化を目指します。PDCAや5Sといった改善活動を土台にしながら、経営レベルまで品質志向を根づかせることで、持続的な競争力を確保することが可能になります。
品質保証(QA)における現代の課題
かつて品質保証は製造業を中心に考えられてきましたが、現在ではソフトウェアやサービス分野にも広がり、従来にない課題が顕在化しています。
ここでは、代表的な課題とその背景について解説します。
スピードと品質の両立
市場の変化が激しい現代では、開発スピードを優先するあまり、品質が犠牲になるケースが少なくありません。特にアジャイルやDevOpsといった高速開発手法の浸透により、短期間でのリリースが常態化しています。
こうした状況下で品質を確保するには、テスト自動化やシフトレフトの導入など、効率的かつ戦略的な品質管理体制の構築が不可欠です。
スピードと品質の両立には、技術とプロセスの両面からの工夫が求められます。
属人化によるリスクとナレッジ継承の課題
品質保証の現場では、特定の担当者に知識やノウハウが偏る属人化が深刻な課題です。
属人化が進むと、担当者の異動や退職により業務が滞ったり、品質基準が継承されずにミスが再発するリスクが高まります。
この問題に対応するには、ドキュメント整備や業務プロセスの標準化、ツールによるナレッジ共有が有効です。特にノーコードの自動化ツールなどは、技術知識がない人でもテスト作業を再現可能にし、属人性を排除する一助となります。
品質保証(QA)担当の人材不足
品質保証分野では、専門知識を持つ人材の確保が年々難しくなっています。
特にIT業界では、開発スピードの加速に対し、QA人材の供給が追いついていない現状があります。
この人材不足は、テスト漏れや不具合の見逃しといった品質リスクを高める要因です。対策としては、属人化の回避に加え、ノーコード自動化ツールの導入や、他部門と連携した品質文化の醸成が有効でしょう。
専門人材の負担を軽減しつつ、全体の品質レベルを維持する工夫が求められます。
AIと自動化で実現する次世代の品質保証(QA)
品質保証の現場では、属人化や人材不足といった課題を背景に、AIや自動化技術の導入が加速しています。ここでは、次世代品質保証を支える具体的な技術とその実践例を解説します。
AIとセルフヒーリングによる自動メンテナンス
AIによるセルフヒーリング機能とは、テスト自動化においてスクリプトの保守・修正をAIが自動で行う仕組みです。従来はUI変更などでテストが失敗するたびに人手で修正していましたが、AIが変更点を学習・判断し、自動で対応することでメンテナンスの負担を大幅に軽減できます。
これにより、属人化や人材不足といった課題にも対応可能となり、安定した品質管理体制の継続が現実的になります。AutifyのようなAIテストツールは、この機能を搭載しており、次世代品質保証の要ともいえる存在です。
ノーコード自動化ツールがもたらした活用事例
テスト自動化の真価が問われるのは「頻繁なUI変更」「多様なブラウザ対応」「手動工数の肥大化」などの現場です。Autifyは、ノーコードで誰でも簡単にテストシナリオを作成でき、こうした課題に効果的に対応できます。
例えば、頻繁なリリースに追従するUIの変更に対しても、AIが自動で修正候補を提示するため、メンテナンス工数が大幅に削減されます。
また、専門的なスキルがなくても操作できるため、品質保証以外の職種とも連携しやすく、全社的な品質向上にも貢献しています。結果として、開発サイクルの短縮と品質の安定を同時に実現可能です。
まとめ
品質保証と品質管理は、製品・サービスの信頼性を支える重要な柱です。
特に現代では、ソフトウェアに限らずあらゆる業界で品質への要求が高まっており、プロセス全体における改善が求められています。
シフトレフトやAIの活用、ノーコード自動化ツールの導入といった最新の手法を取り入れることで、品質向上と効率化を両立することが可能です。今後の品質保証活動においては、テクノロジーと人の知見を融合し、持続可能な品質管理体制を築くことが重要でしょう。